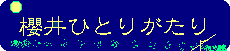「かくれんぼ」
夜が明けた。
孝太はオニのままだった。夜通し探したが、一人の友も見つけられなかったのだ。
境内に青くただよう靄に向い、「もういいかい」と呼んでみた。すると、「まあだだよ」いう声がして、庫裏の陰から背の高い女がひとりあらわれた。
女は、夕暮れがそこだけ取り残されたようないでたちをしていた。血の気のない顔色の中で唇の紅が鮮やかに燃えていて、
紅葉色の着物の裾からも、やはり真紅の襦袢がのぞいていた。
「おねえさんも、遊んでて朝になっちゃったの」と、孝太は訊ねた。
「ううん、遊ばれてて朝になっちゃった」
「遊ばれてて?」
「そう、私はちっとも楽しくない。相手ばっかりが喜んでるのよ」
「子供は勝手だからね」と、孝太は大人ぶった口調で言った。それがおかしかったのか、女は唇に指を添えてくすりと笑った。
「ちがうわ、大人相手だから楽しくないの。あなたみたいな子供は大好き」
「じゃあ、いっしょに遊んでくれる?」
「ええ、いいわ。何して遊ぶ」
「オニごっこがいい。もちろん僕が逃げる役」
「そうね。私もいちどオニになって、誰かを追いかけてみたかったんだ……」
二人は、羽が生えたように境内を飛び廻った。つい夢中になって、手入れのゆきとどいた庭に足を踏み入れても、彼らをとがめる人はいなかった。
表の石段を式服姿の人々がのぼってきた。先頭の男性は白木の位牌を抱いている。その後ろには、妻らしき女性と、親戚とおぼしき男女が付きしたがっている。山門をくぐった彼らに気付くと、地に靴底を滑らせながら孝太は立ち止まった。
「父さん達だ!」いったん女を振り返ってから、孝太は列の側に駈け寄った。
「父さん、母さん」飛び跳ねながら彼は両親に呼びかけた。なのに、ふたりとも、いっこう我が子に気付く気配はない。
「ねえ、どうして知らん振りをするの」と叫びつつ腰にすがろうとしても、腕はむなしく宙を掻くばかりだ。
そのうち女が見かねたように、うしろから彼をかかえこんだ。
「お父さん、お母さんには、あなたの声が聞えない。姿だって視えないのよ」
「なんで」孝太はとうとうベソをかきだした。
「それが、かくれんぼのきまりだから」
両親たちが本堂にあがって間もなく、和尚さんがあらわれた。短い説教の中に「四十九日」という言葉が聞き取れた。
お経がはじまった。孝太は「うっ、うっ」としゃくりあげながら、父母の背中を見つめていた。女はそんな彼をふところに包み、ほてる耳たぶに唇を寄せて慰めをささやいた。
「そんなに泣かなくていいの。あのお経が済んだら、あなたはとってもすてきな処へ行ける。そこでは、たくさんの友達と一日中遊んで過ごせる。さみしいなんて泣いてる暇はないわ」
この言葉を境に、不思議と孝太の身は軽くなった。さらに読経が終りに近づくにつれ、宙に光の粒があらわれては数を増し、ついにはそれらが集まって、大きな金色の河を描き出した。
対岸には声をあげてはしゃぐ子供等の姿があった。あるものは何ごとか呼びかけながら、こちらに向かって手招きをしている。孝太の想いは早や父母を離れ、彼方に待つ愉楽の日々へと翔びたとうとしていた。
やがて時を告げるように、高く鈴(りん)の音が鳴りわたった。徐々にしりぞく余韻とともに、孝太の姿はかき消えた。ひとり残された女は、よろめき加減の足取りで庭の方に歩いていき、池の辺の石組みにぐったり凭れかかった。
今日もまた、御ほとけの掌からこぼれたらしい。
「もういいかい・・・・・・」
つぶやいた彼女の目から白い露が糸を引き、足もとの杉苔が小さな珠をいただいた。けれど、根締めの笹の葉がささやかな風にそよぐと、そのわびしげな姿も‘すうっ’とかすれて視えなくなった。
了
|